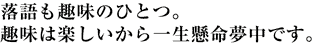
文化庁2003年度芸術選奨文部大臣賞受賞。名実ともに落語界の看板として各方面で活躍中の柳家小三治さん。多趣味で有名で、落語も趣味と語る小三治さんにお話を伺いました。
(Q:えずこホール、K:柳家小三治さん)
Q.高校時代に落語研究会に入部し、ラジオ東京の「しろうと寄席」で15週勝ち抜きで頭角を表したとお聞きしましたが。落語はかなり前から始められてたんでしょうか。
K. 落語に出会ったのは、この道に入る者としては遅くて、中学三年の終わりごろ、丁度受験のときでした。
私は落語が聴きたい。親は聴かせたくないということで、随分親と喧嘩しましたね。本屋で落語全集を見つけて、げらげら笑って、世の中にはこんな面白い物があるんだって目覚めたんですね。そうなるともう止まらなくて、高校入っても自分で勝手に節をつけてやってました。
そしたら落語研究会ってのが今年から出来たんだけど入らないかって誘いがきて、それで入ったんです。 子どものときからやってたんでしょうってよく言われるけど、出会ったのは子どもとしては晩年ですね。
Q.大学一浪中、両親の反対を押し切り、柳家小さん師匠に入門。親御さんからはかなり反対されたそうですが…。
K. うちの親父は学校の先生でした。出身は今の宮城県岩沼市、槻木から岩沼市に入ってすぐのとこですけど、高等小学校を出てすぐ村の代用教員になって、きっと石川啄木みたいな感じだったのかな。
それで、日本一の小学校の先生になるんだという夢を抱いて、跡継ぎだった農業をお姉さんに譲って東京へ出てきたっていう経緯がありましたから、まさか自分のせがれが噺家になるなんて思わなかったんでしょうね。
お袋は、亘理町の出身で人間としてはお袋の方が固かったですね。
親父のほうはそんなに好きならしょうがないって許してくれたけど、お袋は死ぬまで許さなかったですね。家からこんなものが出るなんてとんでもないっていう話ですね。
Q.69年真打ち昇進、十代目小三治襲名。29歳で真打ち昇進は当時としてはかなり早い昇進だったと思うのですが…。
K.次はお前が真打だぞっていうのは、もう何年も前からいろんなところから情報は入ってましたので、そんなに驚きはしなかったですね。真打とか二つ目というのは、言ってみれば係長だ、課長だ、部長だってなもんですが、落語の世界は組織ではなくて、一人一人が一国一城の主なわけで…、私は、ほんと言って肩書きなんてどうでもいいと思ってるんですよ。
だから真打になるならないということよりも、お客さんに喜んでもらえるかどうかっていうことのほうがずっと大きい問題で、お客さんに喜んでもらえたら生涯真打にならなくてもいいと思ってました。
なんとか賞受賞っていうのも、世間では受賞するとこの人凄いんじゃないかって思われたりしますが、逆に言えば受賞しても大したことない人は大したことないわけであって、私の受賞も、たまたまそういうめぐり合わせだったということ。
聴いてくれた人が今日は面白かったといって幸せになってくれることが私にとっての受賞です。
Q.私にとって、落語は職業、仕事ではなく趣味のひとつ。生きることそのものが趣味なんです。仕事はノルマをこなせばいいものでしょうが、趣味は楽しいから一生懸命、夢中です。と、あるインタビューでお話しされてましたが、それほど夢中になれる落語の魅力とはどんなところにあるのでしょうか。
K.わからないですねぇ。なんでこんなに面白いんですかね。65になりますが、まだまだ面白いっていうか、人生を生きてていろいろ楽しい事や辛いことに出会いますよね。
そんな経験を重ねることによって、ああそういうことかって膝を打つことがたくさんある。 共感、あるいは慰め、あるいは安堵感といっていいかもしれない。あっ、そういう人がいるんだ。じゃ俺もこんなんでいいんだ、とか、噺の中に少し愚かなやつが出てくると、ばかだねぇ、と思いつつも、どっか俺のこと言われてるんじゃないかって思ったり…、そういう面白さがいちばんじゃないですかね。
だから落語は生きてることをやってる限り面白い。皮肉な言い方すれば、生きることをしてない人は落語聴いても面白くないんじゃないかな。
Q.今のお話に繋がるんですが、「落語がどうして今まで続いてきたかというと、先輩たちが残してきた話をいま生きてる私たちが面白いと思うからやる。それが結果的に伝統ということかも知れないけれど、絶やさないとか守るというのではなくて、なくなるものはなくなってもいい」ということをおっしゃってたんですが、そのへんのところのお話を…。
K.伝統芸能というのは、振り返ってみてはじめて、これは伝統になってるなって思うわけで、そのときそのときは、面白くてやりたくてやってきたわけです。伝統芸能を守ろうなんていう使命感なんてどこにもなくて、面白いから、やりたくってしょうがないからやってきたんですよ。
そういう人が次々続いてきたんで、それが伝統っていう言葉で言い表わされるようになったんじゃないですかね。世間でよく言うじゃないですか。守りに入ったらお終いだって。攻めなきゃ駄目ですよね。攻めるっていうことは、傷ついたり、血を流すことも当然あるわけです。でも、それをやってるから面白いんじゃないんですかね。
Q.「寄席の一日の出演者というのは、人間世界の再現でもある。それで、寄席にある曖昧さというのがとても好きで面白いんだ。」ということをおっしゃってましたが、それが落語の真髄というか、魅力の一つのポイントなのではないかと思うのですが…。
K.それは私の生まれとも関係あると思うんですが、家は曖昧というものを許さなかった家系で、曖昧なものはいけないと思って育ってきて、私もそう思ってるんですが、人間って曖昧さとか緩みとかないとはじけてしまうということを、噺家になってやっと感じさせてもらった。
守るべきところはきちんと守らなければならない。それは間違いなくそうなんです。しかし、それ以外は楽にゆったりしていればいいんですよね。じゃ、どことどこを押さえてしっかりしてなければならないのか、というのを探るっていうのがこの世界に入っての修行でしたね。
そのためには辛いこともありましたけど、そういうところを通り越してくると、ポイントは押さえて、それ以外はゆったりしていること、というのが経験とともに見えてくる。でも、この歳になってもまだ面白いし、ああそうだったのかって迷ってたりする。
よくベテランとか言われますが、私は全然ベテランの気はしてません。ほうぼう部品は古くなっちゃって、いてえとか、眼鏡掛けないと見えないとかやってるけど、まだ、これでいいのか、面白いもんないか、美味しいもんないか、素敵な人はいないかとか、何かを捜し求めて生きてますね。
Q.「無駄とわかりつつ、金を出して噺を聞く。そこに本当のおもしろさがある。無駄なことと分かってする無駄は、これは違う無駄。
江戸では粋(いき)、大阪では粋(すい)という言葉があるが、それは、爛熟したものがどうやって無駄をするかだと思う。
実はそういうことが人の心を豊かにしてくれる」というお話をされてますが…。
K.出世したいとか、肩書きがほしいと思っているうちは粋なんか出てこないですね。江戸時代も安泰の時期が続くと、出世とか、肩書きはいいんじゃない、何も侍ぶって刀さしてれば偉いってもんじゃねえやっていう侍も出てきて、そのへんから侍も本当の人間らしくなってくる。
今でいえば、課長とか部長とか肩書きがあって、「○○部長」とか呼ばれると、あっ俺は部長なんだ、部長らしく何とかしなくちゃとか思う。でもなんともならねえんですよ。ほんとはたいしたことないんだから。そういうところで落語を聴くと、裸の人間と人間との付き合いがあって面白いんじゃないかな…。
(2004年9月23日開催えずこ寄席楽屋にて)
|

